
| 20190629(メモ了) | |||||||||||||||||||||||
|
Jean SIBELIUS(1865-1957) |
|||||||||||||||||||||||
| 【Disc1】 | |||||||||||||||||||||||
| 交響曲第1番 ホ短調 作品39 | |||||||||||||||||||||||
| ①10:35 ②9:18 ③4058 ④11:35 | |||||||||||||||||||||||
| 交響曲第3番 ハ長調 作品52 | |||||||||||||||||||||||
| ⑤10:04 ⑥10:40 ⑦9:11 | |||||||||||||||||||||||
| 【Disc2】 | |||||||||||||||||||||||
| 交響曲第2番 ニ長調 作品43 | |||||||||||||||||||||||
| ①9:06 ②13:29 ③5:59 ④12:55 | |||||||||||||||||||||||
| 【Disc3】 | |||||||||||||||||||||||
| 交響曲第6番 ニ短調 作品104 | |||||||||||||||||||||||
| ①7:57 ②6:09 ③4:04 ④10:05 | |||||||||||||||||||||||
| 交響曲第4番 イ短調 作品63 | |||||||||||||||||||||||
| ⑤9:18 ⑥5:02 ⑦9:11 ⑧9:29 | |||||||||||||||||||||||
| 【Disc4】 | |||||||||||||||||||||||
| 交響曲第5番 変ホ長調 作品82 | |||||||||||||||||||||||
| ①12:42 ②8:48 ③9:10 | |||||||||||||||||||||||
| 交響曲第7番 ハ長調 作品105 | |||||||||||||||||||||||
| ④22:03 | |||||||||||||||||||||||
| パーヴォ・ベルグルンド指揮/ヨーロッパ室内管弦楽団 | |||||||||||||||||||||||
| 録音/第1,2,3番:1997年10月 RFOホール、ヒルフェルスム、オランダ | |||||||||||||||||||||||
| 第4,6,7番:1995年9月 ウォトフォード・コロシアム、ロンドン、英 | |||||||||||||||||||||||
| 第5番: 1996年12月 ナイメヘン、オランダ | |||||||||||||||||||||||
| CD/4枚組/2012年1月/クラシック/交響曲/タワーレコード/WMJ/邦盤 | |||||||||||||||||||||||
| (Ⓟ&ⓒ 1998 Finlandia/Warner) | |||||||||||||||||||||||
|
<★★★★>
|
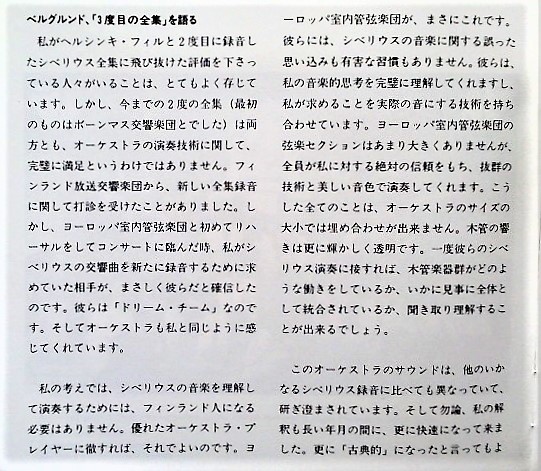
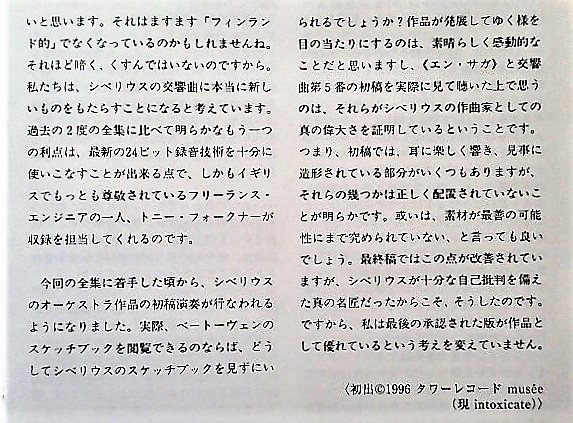
|
(初めの2ページのみ。インタヴューは長くて、省略します)
Disc1&2;
|
| たまに聴くこともあった1番と、しこたま聴いた2番は、ちょっとスケール感が不 |
| 足かもしれないですね。だからそのためにちょっとだけ力んだところがあるよう |
| な気もしますが、キズというほどでもない。 |
| そのまんまじゃ、シベリウスのスコアは鳴ってくれないのだと、ベルグルンドさ |
| んは仰っている。ならば作りものっぽく響くかというと、決してそんなこともない。 |
| ということで、結果、今まで聴いたどの演奏よりすっきりしている。外連のなさも |
| そう。その点が好みの分かれ目。 |
| といってもワタシはこの演奏が好きかどうか、まだよくわからないですね。こう |
| いうのもありなんだということはわかった。生き生きしているように思えるし、甘 |
| いメロディなど化粧っけがなくて初々しい。この感覚はワタシのスタンダードに |
| なるかもしれないとは言えるかも・・・ |
| それよりは3番。このセットものを手に入れた目的の一つ。 |
| ちゃんと聴いたのはひょっとすると初めてじゃないかな。 |
| 出だしの一種のやぼったい常動的曲調が若い時には気に食わなかったかもし |
| れんが、地味さが素朴な田園ふうな滋味に通じて、とても魅力的に感じました |
| ね。第1楽章の常動的ミニマル的曲調をスローに変えたような第2楽章はその |
| 鄙びた感じがとてもいい。ワタシはこの3番の中でも最も気に入りました。第3 |
| 楽章は、やはり出だしの常動的曲調を今度は逆にもっと早くしたような曲調で |
| はじまり、次はモヤーッとした曲調。そして両者が融合してゆくように進み、少し |
| だけ盛り上がって終る。 |
| 人気は確かに出にくいと思います。でもほとんど知らなかったワタシとしまして |
| は、申し訳なかったな。そんな気がします。 |
| 1番2番の若々しさや明るさや外連味がすっかり影を潜めてしまって、5番ほど |
| のカッコの良さにはまだ遠いものの、4番以降の“魅力的な陰気”の世界にぐ |
| っと近い。そうだったんですねぇ。 |
| そうそう、第1楽章の途中で指揮者のひと声(「ウッ!」とかいうの)が聞こえ |
| ました。消さなかったんだ・・・ |
| Disc3&4; |
| 4番。やっぱりいい曲。 |
| また惚れ直した感じ。 |
| ただ、なんで6番/4番の順なのか、4番/6番でないのか、わからなかった。 |
| どの楽章もさりげなく閉じるという6番もグッド! |
| ワタシはもともと4番から、数字のとおりの順で好きでしたが、4番以降は横一 |
| 線という感じに変わったかもしれませんねぇ。 |
| 5番は、4番以降ではサウンドがあか抜けていて外連味もあるので聴きごた |
| えがあるし、第2楽章など非常に美しいのですが、ワタシにはやっぱり第1楽 |
| 章と第3楽章のコーダが特徴的。それがきまっていました。なかなか力感も |
| 出ていた。 |
| それが7番になると、少しのっぺりするのかなと思ったら、ぜーんぜん。この |
| 単一楽章でできた交響詩のような曲が、美しいメロディをばらまいて山あり |
| 谷あり。久しぶりに聴きましたが、きびきびして若々しさを感じましたね。まあ、 |
| シベリウスはこの時点ではそんなにジジイでもなかったわけですけどね。 |
| * |
| 例えばこんな言い方ってできるかもしれません。 |
| ベルグルンド3度目のシベリウスの交響曲全集は、若いメンバーが多く技術 |
| 的に非常に優れた室内オーケストラを核にしたもので、感覚だけでなく熟考 |
| の上で構築された演奏なんじゃないか。ライナーでベルグルンドさんの喋りを |
| 読んだからかもしれませんけどね。結果、曲‘本来’のテクスチャーがよく感じ |
| られる演奏に到達している。(なんてわかったようなこと書いてもいけないん |
| ですが) 敏捷で、かなりスリム、余計なごつさのない“筋肉質”とでもいいま |
| すか。 |
| 昔、カラヤン(1番3番は知りません)でムードたっぷりに聴かされてはまった |
| 音楽(これはこれで今でもいいものだったと思いますが)とは目指すものがす |
| っかり違い、感覚的には新しい。暗さよりもむしろ明るいくらい。まあ空は晴れ |
| てないんだけどね。 |
| このあたりでやめておきましょう、素人の限界です・・・ |
| 梅雨に入ってから、メモをしました。 |
| 車中の音楽としてまったく具合悪くなかった。 |
|
CDが4枚入るプラケース、職場のすぐ近くの100円ショップで探したらすぐ見
つかりました。
|